大石道夫氏セミナー「私と化石」 ― 2017/03/31 09:52
昨日(2017年3月30日),北大総合博物館で大石道夫氏のセミナー「私と化石−DNAから進化の謎を探る−」がありました。
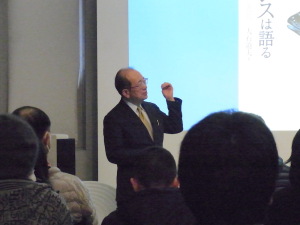
講演する大石道夫氏
大石氏の本業は,セミナーの副題にある,DNAから生命の進化を探る分子生物学・分子遺伝学です。一方,約1億年前の様々な化石を集めていて,世界的にも貴重な化石を所有しています。きっかけはブラジル・セアラー州,アラリペのサンタナ層やクラト層から産出する保存状態の良い化石を見たことです。この時代の,水中・陸上・空中の動物,植物の化石に的を絞って50年にわたって収集してきました。
それらの化石の写真を次々に紹介しました。ワニ,翼竜,シーラカンス,カメ,様々な昆虫,クモ,カエル,サソリ,ほかの魚に飲み込まれそうになっている魚,泳いでいるままの姿の魚,大きな魚に飲み込まれた小さな魚などの化石で,見ているだけで面白い化石が映し出されました。
「生きている化石」と言われるシーラカンスは,1938年に南アフリカ・イーストロンドンの博物館のラティマー女史によって記載されました。その後,マダガスカル北西でも発見され,さらにインドネシアでも発見されました。アフリカ大陸東側のインド洋の種とインドネシア付近の種と二つの種が識別されています。
魚が陸に上がった証拠となる3億7,500万年前の化石も発見されています。カナダ北極圏で発見されたチクターリクと命名された化石です。
化石からDNAを取り出すことはできないのだろうか。化石DNAは5万年から20万年くらいは保存されますが,それより古いDNAは保存されません。
人やチンパンジーのゲノムサイズは約30億です。これに対して,肺魚は50〜100億のゲノムサイズを持っています。この中には意味のないもの(ジャンク)が多くあり,ゲノム解析を困難にしています。
大石道夫氏は,北大教授であった大石三郎氏のご子息です。大石三郎氏は,北大地質学鉱物学科第二講座の第2代教授でしたが,1948年に45才で亡くなっています。
今回のセミナーは,現在,北大総合博物館で開かれている「北大古生物学の巨人たち」(2017年4月2日(日)まで)関連セミナーとして急遽開かれたものです。
なお,今回のセミナーの主な内容は,「シーラカンスは語る−化石とDNAから探る生命の進化」(大石道夫,2015年5月,丸善)に詳しく書かれています。この本には「大石コレクション」の化石写真が,モノクロですが掲載されています。
コメント
トラックバック
このエントリのトラックバックURL: http://geocivil.asablo.jp/blog/2017/03/31/8436265/tb
※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。
コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。