北大公開講座「北海道の地震と防災」 ― 2023/12/16 20:04
2023年12月2日(土)と9日(土) に、北海道大学大学院 理学研究員 附属地震火山研究観測センターの公開講座が開かれました。どちらの日も、午前10時30分から午後4時過ぎまで、昼休みを1時間挿んでの講座です。会場は北大理学部の3号館3階の講義室でした。12月2日のプログラムは、以下のとおりでした。12月9日は防災に的を絞った講座になっています。
谷岡勇市郎氏(センター特任教授):あいさつ・ガイダンス
西村裕一氏(センター准教授):巨大津波に備える
室谷智子氏(国立科学博物館 理工学研究部 研究主幹):歴史資料から巨大地震災害をどう学び、どう残すか
高橋浩晃氏(センター教授):北海道周辺に発生する地震

津波はぎ取り標本を手に説明する西村氏

廊下に展示された津波はぎ取り標本
一番上の肌色の層は1663年噴火の有珠b火山灰、その下の灰色の砂層が1611年慶長地震の津波堆積物、黒色の腐植土の上位の灰色の薄い層が10世紀の白頭山火山灰です。
西村裕一氏の話
堆積物を調べることによって津波発生の履歴を明らかにすることができます。例えば、厚真町で行ったトレンチでは、3000年の間に5回の噴火と1回の津波があったことが明らかになりました。トレンチの壁面をはぎ取ると、時間と場所の記録が得られます。巨大津波があったことが分かると気持ちの準備をすることができます。
津波発生の長期予測の根拠は何でしょうか。
100年前以降であれば写真、映像、調査記録、地震計や検潮儀の記録が残っています。
400年前(江戸時代初期)以降では、古文書、絵図、伝承が残されています。北海道では1640(寛永17)年の駒ケ岳の噴火と山体崩壊による津波、1741(寛保元)年の渡島大島の山体崩壊による津波がありました。乙部町にはヤスの跡のある地蔵が残っています。津波で溺死した人をヤスで突いて引っ掛けて引き上げたと言われています。
数千年前以降となると地質痕跡から津波を知る以外にありません。1)津波で運ばれた砂や礫が地表に溜まる、2)地形が変わる、3)地震により地盤が陸化したり沈降したりして環境が変わる、4)噴砂によって地下が破壊される、などの現象があります。
地震の発生頻度は規模が大きくなるほど減少します。低頻度・大規模災害が起きます。
津波の地質的痕跡が残りやすいのは沿岸の湿地です。
例えば、十勝の幕別町に源を発して大樹町で太平洋に注ぐ当縁川(とうべり・がわ)の河口には湿原が広がっています。湿原は泥炭でできていて、泥炭の成長速度は年1mmと言われています。このような泥炭湿地に津波によって運ばれた砂が一瞬で堆積します。
2004年12月に発生したインド洋大津波の直後に現地調査を行いました。海岸の低地は一面砂の原になっていました。4年後に訪れた時には、すっかり植生が回復していました。
2011年3月の東北地方太平洋沖地震でも3月中に現地調査を行い、2021年3月にも調査を行いました。
1993年の北海道南西沖地震のあと、日本海対岸のロシア沿海州で津波堆積物調査をしました。ここでは、1983年5月の日本海中部地震と1993年7月の北海道南西沖地震の二つの堆積物が確認できました。
道東の浦幌町のトイトッキ沼の北西で行ったトレンチ調査では、5,000年間で10回の津波があったことが分かりました。1667年の樽前b火山灰 の下に厚い砂層があり、このころ巨大津波が発生したと考えられます。
北海道の太平洋岸の津波は、襟裳岬を境に性質が異なっているようです。襟裳岬より西では中規模の津波が発生していて1回のみ確認されています。それに対して襟裳岬の東では、平均500年に1回の巨大津波(波高10m以上)が5,000年で10回発生しています。ただし、津波堆積物が見つからないのは、地震が起きていない、津波がその場所に到達しなかった、堆積したけどその後の自然現象で残らなかった、洪水などで取り去られた、調査が不足している、などの原因があります。

左は司会の谷岡勇市郎氏、右は室谷智子氏
室谷智子氏の話
1872年にドイツのE.クニッピングらが振り子を使った地震の観測を始めました。日本では、1873(明治5)年に函館気象測量所が体感による観測を始めたのが最初です。1875年には東京気象台(気象庁の前身)がパルミエリ地震計による機械観測を始めました。1880(明治12)年にJ.ユーイングの円盤式地震計によって地震波の連続記録が得られるようになりました。そして1898年に大森式地震計によって世界で最初の地震波の連続観測が開始されました。
科学的な観測が行われる前に起きた安政地震(1855年:安政2年)の時には、なまず絵が大流行し、お守りとしても使われました。さらに遡ると、西暦130年代に中国で造られた感震器があります。
地震計は、東西、南北方向と鉛直方向の揺れを記録するもので、動かない錘に針を付けて円盤上に揺れを記録していました。この方式では、長時間の記録が取れませんので、記録紙を円筒状の筒に巻き付けて記録紙を動かすことによって連続記録が取れるようになりました。地震動を針金で再現して教材として販売しました。日本には130年以上にわたる地震の観測記録が蓄積されています。1899年のアラスカ地震(M7.9)の記録、今村式2倍強震計による大正関東地震の記録などです。この頃の地震の記録紙は、煤を塗った紙でしたので毎日の煤付けが大変な作業でした。また、煤書きの地震記録は円弧状になるためそれを補正する解析が必要でした。
地震の記録から、地震を起こした断層面がどのように滑ったかを推定することができます。余震分布、測量データ、遠地地震の波形、津波のデータなどを使います。
大地震の記録としては、西暦416年の地震や同684年の白鳳地震(南海トラフ地震)が文字として残っています。1847年5月の善光寺地震は絵画で記録されています。古い文字記録は「みんなで翻刻」プロジェクトで多くの人に参加してもらって記録を共有しています。
大正関東地震では、死者10.5万人の内9.2万人が火災で亡くなっています。隅田川両岸の両国付近が最も被害が大きく、沈火したのは9月3日でした。火災のほかに地すべり、液状化が発生しました。神田川の川岸では土砂崩壊が発生しました。大正関東地震の震源は神奈川県西部でしたので、神奈川県では揺れによる被害が大きかったです。
震災復興は、後藤新平が指揮を執り、区画整理を行いました。将来東京には地下鉄が必要と考え、いくつかの道路は広い幅を取りました。小学校と公園をセットで建設する、耐震耐火建築にする、隅田川にかかる橋は美しさと耐久性を考えて設計するなどしました。
科学博物館では、今年9月1日(金)から11月26日(日)まで、「関東大震災100年企画展 震災からの歩み―未来へつなげる科学技術」を開催しました。
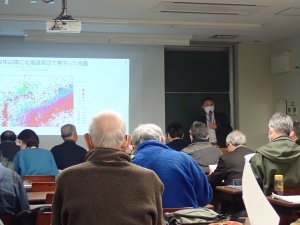
高橋浩晃氏
高橋浩晃氏の話
1919(大正8)年から2023年までの北海道周辺で発生した地震の震央をプロットすると北海道全体、隙間なく地震が発生していることが分かります。
大事なことは、地震予知は現段階では、できないことです。まして、地震が発生する年月日を予知することは無理です。地震を起こす地下の断層が地表に現れた活断層がない地域で地震は起きていますし、これまで地震活動がなかった場所で地震は起きています。国は地震発生の可能性について長期評価を行っていますが、日常生活で使える精度ではありません。道内で比較的地震が少ない地域は、オホーツク海の紋別付近です。
北海道周辺で発生する地震は、1)千島海溝、2)日本海沿岸、3)道東内陸(阿寒-知床)、4)網走沖、5)道南内陸、6)日高山脈南部、7)道央(道北―留萌-空知―石狩―東胆振)に分けられます。
千島海溝から日本海溝北部にかけては巨大地震が繰り返し発生します。2003年の十勝沖地震のあと、大きな地震が起きていません。稀な20年が経過しています。
日本海沿岸は、大地震が時々発生します。1792年の寛政後志の地震、1940年の積丹半島沖地震、1947年の「留萌すぐ沖地震」、1983年の日本海中部地震、1993年の北海道南西沖地震などが発生しています。この地域の地震では、津波の到達時間が0分~17分と短いのが特徴で、高台への避難が重要です。日本海東縁の地震はアムールプレートが年1mmの速さで東に進んでいるために発生します。
道東内陸、網走沖は中規模の地震が散発的に発生します。網走川河口からオホーツク海の海底に延びる活断層(網走湖東方断層)が見つかっていて、1956年には網走沖でM6.3の地震が起きています。
弟子屈から知床にかけての地域はM6の地震が4回起きています。熱水活動が影響していると考えられます。また、新得-上士幌-トムラウシにかけての地域でも地震が起きています。日高山脈南部は中規模地震が時折発生します。道南地域は、函館、松前、厚沢部、乙部などで熱水活動によると考えられる群発地震が起きています。
道央は、地質構造帯の空知―蝦夷帯の西部にほぼ一致して地震が発生していて、中規模の地震が発生するポテンシャルの高い地域です。
千島海溝での地震は、太平洋プレートが年10cmの速さで西に移動し、アムールプレートが年1cmの速さで北西に移動していることによって発生します。根室沖の日本海溝の陸側海底でひずみの測定を行っています。海溝軸の浅い部分にひずみが蓄積していることが明らかになりつつあります。この付近で地震が起きる場合、プレート境界の浅い部分がずれる可能性があり、2011年東北沖地震と同じような巨大津波を発生する地震が起こると予想されます。
浜中町の藻散布沼(もちりっぷ・ぬま)の堆積物の調査から6,000年間で15回の津波が発生していることが分かりました。一番新しい超巨大津波の年代は、1611年あるいは1634年で、すでに400年が経過しています。この地震はマグニチュード9クラスで、津波の最大波高は20mと考えられています。また、根室沖ではマグニチュード8.0~8.5の地震が起きる確率は80%となっていて、超巨大地震の発生が切迫しています。
北海道周辺で発生する地震のモデルは、三陸沖から日高沖の日本海溝モデルと十勝・根室沖の千島海溝モデルがあります。千島海溝の地震では、札幌でも震度6以上になり揺れが3~5分続きます。胆振東部地震の揺れの継続時間は、7~8秒でしたから、異常に長い時間揺れが続きます。
高さ1mの津波が到達する予想時間は、道東で20分程度、道南で40分程度です。釧路、苫小牧、函館の平野部では浸水範囲が広くなります。
被害予想によると、揺れによる死者は160人と見積もられていますが、津波により10万人が被災すると予想されます。
2022年12月から「後発地震注意情報」が始まりました。巨大地震が発生した後、100回に1回程度は本震を上回る規模の後発地震が発生することが分かっています。2011年の東北地方太平洋沖地震では、同年3月9日にマグニチュード7.3の地震が起き、11日に本震があり、3月12日以降、震度6弱の地震が発生しています。このような後発地震にも注意が必要です。
大規模な地震防災対策の特別措置法ができました。これにより地震対策に国が2/3を補助します。北海道は2012年に独自の津波浸水予測を行っていました。これによって浜中町、釧路市、白糠町などは公共施設を高台に移転しました。冬の避難に備えて避難所に薪ストーブとノコギリを備えるなどの工夫も行っています。津波避難タワーの建設も進んでいます。道営住宅を高層化して避難所機能を付加するといった例もあります。
<感 想>
襟裳岬から東での超巨大地震津波の発生は、南海トラフ地震津波よりも切迫しています。予測される被害は、南海トラフ地震による被害よりは小さいとはいえ、最悪10万人の死者が予想されています。311の時は春先でしたが寒さ対策が非常に重要であることが示されました。
昼休みには、廊下に展示してある剥ぎ取り標本を前に西村氏が解説しました。
この公開講座は、2015年度から毎年、計7回「北海道の地震と防災」として開いています。北大の人たちが、粘り強く地震・津波について市民に分かりやすい話を提供し続けていることには感服します。