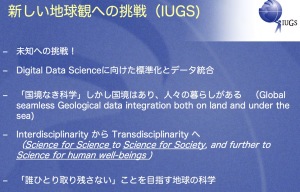市民フォーラム2021「サケに好かれる街、札幌」 ― 2021/02/05 13:53
ちょっと古い話になりますが、2021年1月23日(土)、表記フォーラムがオンラインで開かれました。主催は「札幌ワイルドサーモンプロジェクト(SWSP)」です。
プログラムは多彩で、SWSPの活動報告、フォトコンテスト、札幌大学ウレシパクラブのアイヌの踊り、東京大学准教授の福永真弓さん(環境社会学/環境倫理)の基調講演とパネルディスカッション・質疑応答でした。
「ウレシパ」というのはアイヌ語で「お互いを育て合う」という意味だそうです。

フォーラムの案内チラシ
福永真弓さん:サケ(肉)を好きな社会はサケに好かれる社会になれるのか
フィールドとして太平洋の向こう側のサケについて研究しています。サケを利用するため守っている人たちがいます。カリフォルニアにヒッピーの墓場と言われている所があり、生命地域主義という考え方で、資源を利用しやすい社会をつくろうとしています。1960年代後半に市民と専門家・行政との対立がありました。環境倫理という観点からこれをどうするか考える必要があります。
人新世(アンソロポシーン)と言われる時代、人間の活動が地球環境を変えています。細胞を育ててその肉を食べるという時代が来るかもしれません。細胞サケ肉をつくりデザイナーが切り身の美しさ、寿司の美しさを作り出すようになるかもしれません。
サケを取り戻すと言っても、どんなサケを取り戻すのかを考える必要があります。食べるサケと愛でるサケがあります。野生の鮭は寄生虫がいることがあるので焼いて食べるのが普通です。刺身や寿司で出てくるサケはサーモンと呼ばれています。
サケと生きることを「引き受ける覚悟」が必要です。
この後、パネリストとの質疑応答に移りました。
食育についての質問に対する福永さんの答えは、大人が食べることの背景を理解することが大事だと言うことです。サケに限らず、動物を捕り、殺し、調理し、食べるということの意味を考えることです。
自分で殺すことが出来ない子供がいます。そのような子供には強制はせず、命のつながりを伝わるようにすることが大事だと述べました。
また、札幌の豊平川は、サケの産卵に適した川の姿を考えていることが特徴で、都市住民にとっては条件が良い川だと述べました。サケは公共財と考えて、水や空気と同じ財産と捉える必要があります。
パネリストからは、豊平川を遡上するサケの第一関門はおいらん淵―藻南公園のあたり—で、白川浄水場が第二の関門となっていて、その上流の簾舞にある藻岩ダムから上流には遡上できないとの話がありました。北電に魚道を付けるよう提案していると言うことです。
<感想>
福永さんの話は一部難しいというか、意味のとれない部分がありました。しかし、サケ一つで色々な問題を考えるきっかけが出来ると言うことがよく分かりました。
人工肉の話が少し出ました。培養肉は、2020年暮れにシンガポールで販売許可が下りたそうです。ただし、遺伝子組み換え技術をふんだんに使った物のようで、文明の退化・退廃以外のなにものでもないという意見があります(印鑰智也、FaceBook、2020年12月23日)。
おいらん淵は、昔は今のように岩盤は露出していませんでした。その名の通り淵になっていました。おそらく上流に豊平峡ダムや定山渓ダムが造られて、流れる土砂の量が減ったのが原因だと思われます。しばらく札幌を離れていて、久しぶりに藻南公園に行った時にその変わりようにびっくりしました。
サケの産卵床を河川工事の中で工夫して造っているのは大事なことだと思います。環境に配慮した土木工事です。
人新世は、かなり人に知られる言葉になってきました。『人新世の「資本論」』(斎藤幸平:大阪市立大学准教授)という本が売れているようです。「ひと・しんせい」とも言うようですが、これだと逆重箱読み、つまり訓読み+音読みとなるので「じんしんせい」が良いと思っています。更新世(プライストシーン:Pleistocene)・完新世(ホロシーン:Holocene)とも語呂が似ています。英語ではAnthropoceneで、地質時代としてはアンソロポシーンと読むのが一般的なようです。ただし、アントロポセンも通用しているようです(ウィキペディア、2021年2月5日閲覧)。
いつから人新世かというのは議論が色々あるようです。地質学的な検討は国際層序学委員会(国際地質科学連合の一委員会)で行われていますが、結論は得られていないようです(同上)。
多彩な内容で楽しいシンポジウムでした。
~札幌国際スキーマラソン2021~ ― 2021/02/07 18:28
今年の札幌国際スキーマラソンはバーチャル大会です。
2021年2月7日(日)が、Fun on Sapporo Virtual Race~札幌国際スキーマラソン2021~の開始日で、3月7日(日)までです。25kmに申し込みました。
この日、午前中はよく晴れていて、そよ風のちょっと強いくらいの風で暖かく最高の天候です。モエレ沼公園に出かけました。
まず,1周1kmのコースをダイアゴナル滑走(歩くスキーの滑らせ方)で歩いて身体を慣らしました。それから、1周2.7kmのコースをスケーティングで2周、最後に1kmコースをダイアゴナル滑走して終わりました。 計7.4kmですが、リストGPSの総距離は7.3kmでした。時間は1時間22分かかっていますから、1km11分ちょっと。1カ所だけ200mほどの直線の登りがあります。ここをスケーティングで上れれば時間は大幅に短縮するはずです。それ以外はほとんど平坦です。
気が向いたときにスクワットをやって、それなりに鍛えていたつもりでしたが最後は足に来て何でもないところで転んでしまいました。
今シーズン2回目なので、まだバランスがうまくとれない状況です。3月7日(日)まで楽しみながら走ろうと思っています。
写真1 モエレ沼公園のクロスカントリースキーコース(Epson View による)
中央の四角のコースが1km、右と左のコースを歩くと2.7kmになります。1kmコースの内側に唐松林の周りを回る0.5kmの円形コースがあります。1kmコースと0.5kmコースは歩くスキーのトレースがついているので、公園で貸し出しているスキーで楽しむことが出来ます。
写真2 ガラスのピラミッド脇のスタート地点
まっすぐ林に向かって滑って行って、ちょっとした坂を登って左に曲がります。今日の午前中は最高の条件でした。この記事を書いている午後3時頃には吹雪になりました。
写真3 モエレ山
スタート地点から振り返った風景です。モエレ山は、まだあまり人が出ていません。歩くスキー用のトレースがはっきりとついています。歩くスキーの場合、横滑りすると物凄く体力を使いますのでトレースに沿って歩くのが賢明です。歩くスキーでスケーティングするのは絶対やめた方が良いです。どんなスキーのうまい人でも転びます。
写真4 プレイマウンテン
右がプレイマウンテンです。1kmコースは突き当たりを左に曲がります。スケーティングは右に曲がり坂を登っていきます。
写真5 ガラスのピラミッド
本の紹介:武漢日記 ― 2021/02/14 18:28

方方(ファンファン)著、飯塚 容(ゆとり)・渡辺新一訳、武漢日記 封鎖下60日の魂の記録。河出書房新社、2020年9月。
発行されてから大分経っているので、読んだ人も多いと思います。
2020年1月23日(木)、新型コロナの流行によって人口900万人の武漢市は封鎖されました。その2日後の1月25日から封鎖解除が発表された3月24日(木)までの60日間、著者は毎日ブログを書き続けました。
1月25日のブログは、「私のブログはまだ発信可能だろうか。以前、街頭で下品な言葉を叫ぶ若者たちを批判したとき、私のブログは閉鎖されてしまった」という言葉で始まります。友人の勧めもあり、封鎖中の様子をブログで発表し続けようと決心します。
毎日の文章の頭には短い言葉が置かれています。
1月27日「私たちにはマスクがない」、1月29日「自分を守ることが協力になる」、3月1日「私たちの涙が尽きることはない」、そして3月23日「あらゆる疑問に答える人がいない」、3月24日「私はうるわしい戦いを終えた」。
ネットでの中傷、政府の横暴など、日本も中国もそんなに変わらないなと言うのが最初の感想でした。
市民が置かれた状況は、去年や今年の日本とは比べものにならないほど厳しいものでした。そんな中で市民同士の助け合い、食料をみんなで注文して配達してもらうとか、正しい情報の交換とか、市民が出来ることを懸命にやった記録でもあります。
異常な状態では、記録を残すことに意義があることを痛感しました。
核兵器禁止条約と日本の核軍縮政策に関する討論会 ― 2021/02/15 10:17
2021年2月12日(金)午後5時半から、表記討論会がオンラインで開かれました。主催は核兵器廃絶NGO連絡会で、司会は同会の共同代表である川崎 哲氏でした。
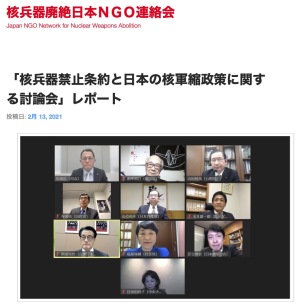
図 核兵器廃絶日本NGO連絡会のホームページ
( https://nuclearabolitionjpn.wordpress.com )
出席したのは、寺田 稔氏(自民党)、浜田昌良氏(公明党)、岡田克也氏(立憲民主党)、足立康史氏(日本維新の会)、志位和夫氏(日本共産党)、玉木雄一郎氏(国民民主党)、福島瑞穂氏(社会民主党)、舩後靖彦氏(れいわ新選組:メッセージ)で、田中煕巳氏(日本原水爆被害者団体協議会・代表委員)、目加田説子氏(中央大学)のふた方がコメントしました。
核兵器廃絶日本NGO連絡会の立場は、2021年1月に出された提言書「核兵器禁止条約が発効! 日本は条約批准に向けて、核依存からの脱却を」で示されています。
(提言書は、核兵器廃絶日本NGO連絡会のホームページ「 https://nuclearabolitionjpn.wordpress.com 」に掲載されています。)
最低限一致したのは、2021年中に開かれる第1回締約国会議へオブザーバーで参加することです。
最大の障害は、核兵器が戦争の抑止力になっているという「核抑止論」で、日本はアメリカの「核の傘」によって守られているという考えです。しかし、国際的に核兵器は違法であるとされたのですから、核兵器の廃絶に向けて踏み出すことが、今求められていると思います。
核兵器廃絶日本NGO連絡会の継続的な努力には敬意を表します。この問題に、一人でも多くの人が関心を持ってもらいたいと思います。
学術フォーラム「新たな地球観への挑戦」 ― 2021/02/16 14:51
2021年1月15日(月)13時00分から17時30分まで、学術フォーラム「新たな地球観への挑戦—地球惑星科学の国際学術組織の活動と日本の貢献—」が、オンラインで開かれました。
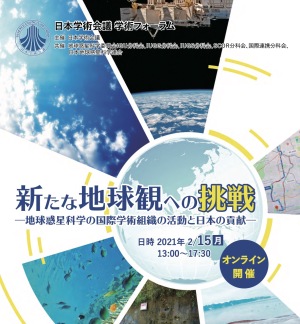
図1 フォーラムの案内チラシ
挨拶や趣旨説明を除いて、12の講演がありました。
国際地図学協会、
国際地理学連合、
国際第四紀学連合、
国際鉱物学連合、
国際測地学及び地球物理学連合、
国際地質科学連合、
海洋研究科学委員会、
世界気候研究計画、
宇宙空間研究委員会、
太陽地球系物理学・科学委員会、
南極研究科学委員会、
国際北極科学委員会
です。
講演の後、西 弘嗣(ひろし)氏(第三部会員:福井県立大学)の司会でパネルディスカッションがあり、沖 大幹(おき・たいかん)氏(第三部会員:東京大学)がまず発言し、話題ごとに各講演者が発言しました。
各講演者の講演概要は、学術会議のホームページからpdfファイルをダウンロードできます。
( http://www.scj.go.jp/index.html>一般公開イベント>
学術フォーラム「新たな地球観への挑戦—地球惑星科学の国際学術組織の活動と日本の貢献—」 )
いくつか講演内容を紹介します。
大谷栄治氏(連携会員:東北大学名誉教授):鉱物が語る自然・環境・社会―IMA(国際鉱物学連合)の活動と日本の貢献―
国際鉱物学連合は、1958年に39カ国が参加して創立されました。
重要な役割として、鉱物に名前を付け、分類し、情報を収集整理することがあります。国内では2009年に発見された鉱物として、千葉県のメタン含有珪酸塩鉱物である千葉石や房総石があります。九州の西の端からはマイクロ・ダイヤモンドが発見されています。
高温高圧下での鉱物研究で日本は先端を走っています。放射性廃棄物処理やバングラデシュでのヒ素処理などでも鉱物学は重要な役割を果たしています。宇宙での新鉱物の発見や医療鉱物学といった分野も発展しています。
北里 洋氏(東京海洋大学):チバニアンの背景—IUGS(国際地質科学連合)の活動と日本の貢献—
千葉県・市原市の養老川河岸の露頭が、77.4万年前の更新世中期基底の国際標準模式層断面及び地点(GSSP)に認定されました。
これが決定される大きな要因として、地磁気のデータがそろっているということがありました。日本での地層の残留地磁気研究は、松山基範(もとのり)が世界で初めて地磁気逆転を発見して以来の歴史があります。
地質時代を定義することは標準化の基礎であり時空間性を保証するものです。縫い目のない全球地質図を作成する上でも欠かせません。全球を覆う地質図やヨーロッパ全体の地質図、海底鉱物資源分布図などもつくられています。
国際地質科学連合は1961年に設立され、アメリカ財務省認可の非政府組織(NGO)です。「全球規模の、公平な、非政治的な、そしてどの政府にも加担しない組織」です。122カ国が加盟し、57の国際学協会が提携しています。
図2 新しい地球観への挑戦(IUGS):IUGS Presentation(北里,2021.学術会議ウェブサイト資料から)
藤本正樹氏(JAXA宇宙科学研究所):宇宙開発の新展開と国際ルール—COSPAR(宇宙空間研究委員会)の活動と日本の貢献—
はやぶさ2が小惑星リュウグウからのサンプル・リターンに成功しました。約5.4gのサンプルを持って帰り、オーストラリアの砂漠にカプセルが着陸しました。このプロジェクトは、オーストラリア政府との合意の下で実行されました。
宇宙物質を地球に持ち込んでも良いという世界的合意が必要です。
これには二つの面があります。一つは探査対象天体の汚染を防ぐということ、もう一つは地球が探査天体の微生物などによって汚染されないということです。COSPARの下のパネルで合意形成を行いました。安全基準をカテゴリーごとにクリアする必要があります。
現在、火星からのサンプル・リターンが計画されています。日本は、火星の衛星フォボスからのサンプル・リターンを計画しています。フォボスには微生物がいる可能性があります。そこで、まずフォボスの周りを回りながら観察し、その後着陸し、さらにサンプル・リターンを行う計画です。地球への影響を検討する必要があります。
月に関しては民間の小型着陸船で旅行するビジネスが考えられています。この場合も、世界的規模での合意形成が必要です。
<感想>
四時間半の長丁場でしたが、興味深い話を幾つも聞くことが出来ました。
どの学会も若手の育成に力を入れていること、市民への科学の普及を視野に入れていることがよく分かりました。