本の紹介:見えない絶景 深海底巨大地形 ― 2020/07/01 19:57

藤岡換太郎,見えない絶景 深海底巨大地形.ブルーバックス,2020年5月.
深海に何回も潜っている著者の経験を活かし,最初は仮想潜水艇「バーチャル・ブルー号」による世界の深海底を一巡りする旅です.
日本海溝からはじまって,海溝の大洋側にある火山・プチスポット,深海に広がる玄武岩の広大な大地・シャッキー海台,ハワイのホットスポット,海嶺を切るトランスフォーム断層,太平洋プレートの湧き出し口である東太平洋海膨,日本海溝と違うタイプのチリ海溝,太平洋中央海嶺,中央インド洋海嶺,房総半島南東にある海溝三重点・坂東(ばんどう)深海盆を見て回ります.
グーグルアースには海底地形も表現されているので,それを見ながらそれぞれの場所に行った気分になれます.
後半は,深海の巨大地形がどうしてできたのかを中心に,プレートテクトニクスの始まり,40億年前以前(冥王代)に地球に何が起こったのか,深海底と宇宙の関係の話です.
これらの中で最も興味深かったのは,ハワイの溶岩湖での観察事実です.
溶岩湖の溶岩の表面が固まり「かさぶた」ができ(プレートの形成),ほとんど時間をおかず,その固まった溶岩に裂け目(海嶺)ができ,新たに溶岩が吹き出し,裂け目を横断する切れ目(トランスフォーム断層)ができ,別の場所では,「かさぶた」に直線状の凹みができて両側から「かさぶた」が潜り込んでいきました(沈み込み帯:海溝).「海溝三重点」まで溶岩湖にできたというのです.
これは,Wendell A. Duffield(1972,Journal of Geophysical Reseaech Vol.77,2543-2555)に載っているそうです.プレートテクトニクスがどう始まったのかを,かなりよく説明できるように思いました.
現場をよく知っているからこその,おもしろい話がたくさん詰まっています.
雨竜沼湿原 ― 2020/07/07 15:55
2020年7月3日(金),雨竜沼湿原へ行ってみました.風もほとんどない穏やかな天気で,ゆっくりと湿原を一周して戻ってきました.2008年のお盆に行って以来12年ぶりの雨竜沼湿原です.
雨竜沼湿原一帯は,恵岱岳(えたい・だけ)玄武岩類と呼ばれる,かんらん石を含む玄武岩質溶岩が分布しています.その下位には,かんらん石を含む輝石安山岩の火山角礫岩が分布しています.
玄武岩質溶岩の下底は高温酸化により赤褐色となった凝灰岩状の岩相があるようです.この層が地表水の地下への浸透を防いでいて湿原が出来たのではないかと考えています.
玄武岩質溶岩は,南西に緩く傾斜した面を形成していて雨竜沼湿原に地下水が供給されやすい地形となっています.
恵岱岳玄武岩類の上位には,主に安山岩溶岩からなる南暑寒岳溶岩が分布していて,湿原に向かって緩やかな地形が広がり,やはり地下水の供給源となっていると考えられます.
このような地形的,地質的条件によって雨竜沼湿原が出来たものと考えられます.
写真1 恵岱岳(標高1060m)
中央付近の四角に見えるのが恵岱岳です.左に緩く傾斜した溶岩の流走面が見えます.左手前の白い筋が尾白利加川支流のペンケペタン川で,雨竜沼湿原から流れ出ています.左端の白い平地が雨竜沼湿原と思います.
昔,稚内空港から札幌丘珠空港への路線がありました.たまたま,飛行機が恵岱岳の近くを通り,雲もあまりなかったのでテーブル状の恵岱岳の写真が撮れました.
雨竜沼湿原は標高850m 付近の台地に広がっています.東西4km,南北2km で,多くの沼が点在する高層湿原です.
高層湿原というのは,湿原の草などが枯れて腐らず堆積してできた泥炭の表面が,周囲からの水が流入しない高さになった湿原のことです.標高の高い所にある湿原ではありません.雨竜沼湿原では,小さな沼のずっと下をペンケペタン川が流れています.
図1 雨竜沼への道
標高540mの南暑寒荘までは車で行けます.この日は金曜日でしたが,かなりの車が停まっていました.
白竜ノ滝から先が,転石がゴロゴロした急な道になります.恵岱岳玄武岩類の平坦な面に出ると緩やかになり湿原に到着です.登山道が横切る小川の手前左にブラシがかかっているので靴を洗って湿原に入ります.入ってすぐの所に休憩用の木の台があります.湿原を一周してここまで戻ると約4.5Kmです.湿原の木道は時計回りに歩きます.
写真2 管理棟と恵岱岳の玄武岩質溶岩
右奥の建物が管理棟で,その向こうに恵岱岳の溶岩の一部が見えます.独立峰のように見えますが突き出した尾根で,ここからの比高は450m あります.
右側の白い建物は発電機が収められています.左の建物がトイレで,その左奥に南暑寒荘とキャンプ場があります.今年は南暑寒荘は閉鎖です.
写真3 砂岩・礫岩層と安山岩溶岩と玄武岩溶岩
「国領」図幅によると鮮新世・留萌層の信砂(のぶしゃ)火山噴出岩層と恵岱岳の玄武岩質溶岩です.下から,西に20°ほどで傾斜した砂岩・礫岩,安山岩溶岩,その先に左に緩く傾斜した玄武岩質溶岩です.砂岩・礫岩は,この崖の下の方ではシルト岩になっているようです.一番上の玄武岩質溶岩は恵岱岳の噴出物です.
写真4 砂岩と安山岩溶岩の境界
柱状節理の発達した安山岩溶岩の直ぐ下には,自破砕状安山岩があります.
写真5 恵岱岳の玄武岩質溶岩
登山道の標高830m 付近に出ている玄武岩質溶岩の露頭です.川が登山道に迫っているところです.
写真6 玄武岩質溶岩の高温酸化部
きれいなレンガ色をした高温酸化部です.前の写真のちょっと上流の登山道脇に出ています.この層が降水の地下への浸透を少なくしていて,湿原成立の重要な役割をしていると思います.この付近では標高830m が恵岱岳の玄武岩質溶岩の下底のようです.
写真7 暑寒別岳(標高1492m)
遊歩道分岐点の少し手前(東側)から見た暑寒別岳です.白い花はワタスゲ(綿菅)で,黄色はゼンテイカ(禅庭花:エゾカンゾウ)です.
写真8 南暑寒岳(標高1296m)
同じ所から見た南暑寒岳です.恵岱岳玄武岩類よりも新しい安山岩溶岩でできています.尾白利加川の源流となっています.
風がほとんどなく穏やかな天気でした.ゆっくりと湿原を廻ることが出来ました.
写真9 池塘(ちとう)
湿原のほぼ中央付近の池塘です.池塘というのは,高山の湿原や泥炭地にある池や沼のことです.
写真10 湿原を蛇行しながら流れるペンケペタン川
川は湿原から一段低いところを流れています.遊歩道合流点の東400m 付近です.
写真11 湿原からの川の落ち口
この先で恵岱岳の玄武岩質溶岩の分布が切れ,ペンケペタン川は急流となって流下します.登山道の860m 付近です.
登山口に戻ってから,お湯を沸かしコーヒーで一服して帰路につきました.良い一日でした.
初夏のモエレ沼公園 ― 2020/07/10 10:50
2020年7月9日, 朝起きたら日が差していました.これは行かなくちゃと,自転車でモエレ沼公園に行きました.
自転車を置いて,モエレ山とプレイマウンテンに走って登りました.2回廻ったところでバテてしまい帰ってきました.
雨上がりで気持ちの良い天気でした.
図1 今日走ったコース
モエレ山の南西地点からスタートしてサミットの緩い坂を上り,モエレ山の242段の階段を上り,プライマウンテンに上って戻ってくるというコースです.これを2周しました.ただし,プレイマウンテンを下りてからのコースは違います.
写真1 モエレ山
手前の芝生も含めて一面の緑です.サミットからの眺めです.
写真2 プレイマウンテン
東の空にはまだ雲が残っています.
写真3 モエレ山から西を見る
中央に手稲山,一番左に藻岩山です.気持ちの良い朝です.
写真4 札幌西部山地
プレイマウンテンから見た札幌西部山地で,手稲山から空沼岳までが見えます.
写真5 モエレ山と札幌西部山地
本の紹介:地球・惑星・生命 ― 2020/07/17 13:14
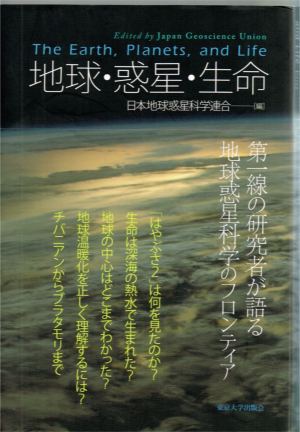
日本地球惑星科学連合 編,地球・惑星・生命.東京大学出版会,2020年5月.
日本地球惑星科学連合は2005年に誕生しました.この時から,JGL(Japan Geoscience Letter)を年4回発行してきました.このニュースレターは日本地球惑星科学連合のウェブサイトで,すべて読むことが出来ます.↓
(http://www.jpgu.org/publications/jgl/)
この本は,同連合の前身である地球惑星科学関連学会合同大会(1990年から開催)からの30年を記念して,JGL の記事の中から選んだ21編を新たに書き下ろして発行したものです.その他に,八つのコラムが載っています.
I 宇宙のなかの地球
II 生命を生んだ惑星地球
III 岩石惑星地球の営み
IV 地球環境の現在、過去、そして未来
V 人間が住む地球
の四部からなっています.
それぞれの執筆者の熱意が伝わってくる内容です.その中で,
2 太陽系小天体探査と「はやぶさ2」:渡邊誠一郎
7 最古の生命の痕跡を探る:小宮 剛
12 地球の中心はどこまでわかったか:廣瀬 敬
15 気候変化が海洋生態系にもたらすもの:原田尚美
19 環境汚染と地球人間圏科学-福島の原発事故を通して:
近藤昭彦
20 防災社会をデザインする地球科学の伝え方:大木聖子
などが,特に記憶に残りました.
それぞれの分野の研究の歴史,現状,これからの課題が述べられているので,特に地球惑星科学を志そうとする若い人たちが,この分野の全体像をつかむのに役立つと思います.
余談ですが,この本の「はじめに」を書いている日本地球惑星科学連合会長の川幡穂高氏の「メールニュース」での巻頭言は,なかなか読み応えのある内容です.↓
( http://www.jpgu.org/publications/mailnews/ )

















