東日本大震災学術調査成果講演会 ― 2014/02/07 10:48
土木学会北海道支部・東北支部主催で,表記講演会が札幌コンベンションセンターで開かれました。この講演会は,2014年に創立100周年を迎える土木学会の記念事業の一つです。
余談ながら,土木学会は1914(大正3)年11月24日に創設されました。主に河川・運河・港湾で力を発揮してきた古市公威(ふるいち・こうい)が,初代会長に選出されました。就任は1915年1月で,古市は62才でした。それから,100年が経過しました。
もう一つ余談ですが,この講演会で紹介された被害の衛星写真が,ほとんど,グーグル・アースによるものでした。日本にも立派な画像を撮っている衛星があるはずですが,活用されていません。
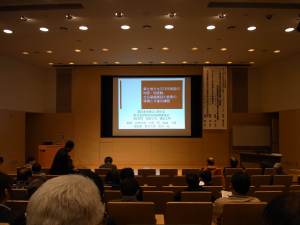
写真1 開会前の講演会場の様子
今回の講演会のプログラムは次のようなものでした。
松﨑 裕(東北大学・助教):東北地方太平洋沖地震の地震・地震動,社会基盤施設の被害の特徴と今後の課題
真野 明(東北大学・教授):2011年大津波による大規模浸食
今西 肇(東北工業大学・教授):宅地滑動の復旧と災害発生物の処理および有効利用

写真2 講演する松﨑 裕氏
松﨑氏の講演内容は,土木学会東北支部学術合同調査委員会の地震工学・構造工学部門の調査結果をまとめた者です。
今回の地震では,本震発生前に西に移動していた地殻変動が,本震の2〜3日前に東へ変位し,本震で大きく東に変位したことが明らかになっています。地殻変動は水平方向に最大5m,鉛直方向に最大1mを記録しました。鉛直成分の大きさは,津波の浸水高と良い相関を示します。
震度は広い範囲で6弱を記録し,その中に6強の地域が点在しているほか,3個所で震度7が記録されています。
国道では,4,400橋のうち960橋で,福島県の県道では4,400橋のうち641橋で被害が発生しています。注目すべき現象として,鋼板とゴムの境界でのゴム支承の破断が起きていることです。
津波では,橋桁の落下や橋脚の圧壊がありました。新幹線高架橋では,端部柱の圧壊のほかに電化柱の折損・傾斜・ひび割れが約540個所で発生しました。
今後に向けた課題としては,付属物を含めた耐震性の確保や修復しやすいかどうかに配慮した設計が必要なこと,大きな応答時に効果を発揮すべき部材に対しては現実に作用する荷重・応答を踏まえた設計が必要なことなどが挙げられます。

写真3 真野 明氏
真野氏は,まず,津波による大規模な侵食の事例を,津波前と津波語のグーグル・アースの写真で示してくれました。
大規模侵食は,まず,第1波の段波の衝撃によって堤防波返しが破損し大量の海水が浸入します。そのあと,戻り流れが弱い部分を破壊していきます。河口堰などがあると堰の脇が戻り流れ出破壊されます。
今西氏の講演は地盤災害についてです。地盤災害のうち自然斜面の崩壊は福島県を中心に発生し,造成宅地は仙台市を始め,広い範囲で深刻な被害が発生しました。液状化によって北上川・鳴瀬川・阿武隈川水系で河川堤防の被害がありました。これらの被害は,地震動の継続時間が非常に長かったことが原因と考えられます。
仙台空港周辺では,津波が襲ってくる前に液状化が発生していることが写真から確認できます。
粘性土の上に砂質土を盛って堤防とした個所では,堤体材料の液状化が発生しています。
津波の圧力に抵抗できなかった建築物があります。大規模構造物では津波の圧力を低減できるピロティー構造とすることのほか,浮力・基礎地盤の液状化・洗掘などを考慮する必要があります。
なお,今回の講演の内容をDVD にまとめたものが,土木学会東北支部のウェブサイトで入手できます。
( http://www.jsce.or.jp/branch/tohoku/ )の右上のサイトです。
コメント
トラックバック
このエントリのトラックバックURL: http://geocivil.asablo.jp/blog/2014/02/07/7214825/tb
※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。
コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。