本の紹介「自然景観の成り立ちを探る」 ― 2014/01/08 11:10
「フィールド科学の入口(全10巻)」の一つとして刊行されたものです。シリーズには民俗学者の赤坂憲雄氏が関わっていることから分かるように,自然科学以外のフィールド科学が多く取り上げられています。
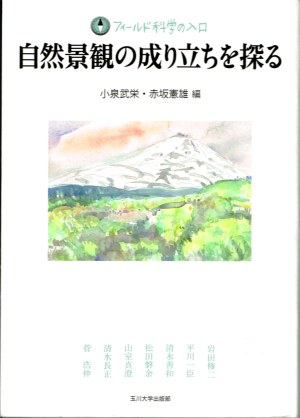
小泉武栄(こいずみ・たけえい)・赤坂憲雄(あかさか・のりお)編,自然景観の成り立ちを探る,2013年10月,玉川大学出版部。
I 部は『「ジオエコロジー」の目で見る』と題して,小泉氏と赤坂氏の対談です。
ジオエコロジーは,「自然景観や植生の分布を,地形・地質の成り立ちや自然史から説明する複合的な分野」と位置づけています。小泉氏がどのようにフィールドに接し研究を行ってきたかを具体的に語っています。フィールドノートをどのように使っているかと言ったことも語られています。
II 部の最初は,岩田修二氏の「中国、天山山脈ウルプト氷河での氷河地形調査」です。
氷河地形調査に出かけた時に持っていった機材一覧から平板測量で氷河の地形測量を行った話など,これも具体的な内容です。最初の調査から20年後に行った調査の結果と何が分かったかを述べています。
次いで,平川一臣氏の「津波堆積物を、歩いて、見て、考える」です。
2011年の東日本大震災の直後に調査に入り,過去の津波堆積物の露頭を見つけた話から始まります。津波堆積物を見つけるのには,どのような地形に注目するのかが述べられています。海岸段丘や砂洲と言った地形と津波堆積物の関係も興味深いものです。
南海トラフの沈み込みによる大地震については,古文書を中心に周期や規模が明らかにされていますが,古い文書の無い北海道太平洋岸では良好な状態で残されている津波堆積物が巨大地震・津波解明の手がかりになります。北海道と三陸の両方の津波堆積物を関連づけて見直すことが超巨大津波の解明のために必要だと述べています。
III 部は,次の5編からなっています。
清水善和氏:小笠原の外来種をめぐる取り組み
松田磐余氏:地震時の揺れやすさを解析する
山室真澄氏:自然は私の実験室 宍道湖淡水化と「ヤマトシジミ」
清水長正氏:風穴をさぐる
管 浩伸氏:サンゴ礁景観の成り立ちを探る
いずれも,フィールドにどう取り組んだかを具体的に述べたもので,さらに,どのような成果が得られたかを述べていて,分かりやすく面白い内容です。
赤坂憲雄氏が編者紹介のなかで,「私の研究に衝撃をあたえた一冊」として民俗学の宮本常一の「忘れられた日本人」(岩波文庫)を挙げています。
「私は長い間歩き続けてきた。そして多くの人にあい、多くのものを見てきた。」という宮本常一の生活は,フィールドワークそのものだろうと思います。
切り口はやや異なりますが「フィールドジオロジー(全9巻)」(共立出版)があります。地質学の分野別に,フィールドでどのようなデータを集めるかを述べたものと言えます。
地質調査などの実際を述べたものとしては,「テーチス海に漂う青い雲−若きフィールドワーカーたちの見聞録」(テーチス紀行集編集委員会,2011年1月,発行:いりす,発売:同時代社)があります。地質,氷河,森林,動物,民俗などの学術調査隊での経験を隊員であった人たちが述べたものです。
この「自然景観の成り立ちを探る」は,自然から何を,どのようにして引き出すのかを教えてくれる優れた「フィールド科学の入口」です。多くの若い人に読んで欲しいです。